【生徒も参加!?】効果的な授業研究にするためのアイデア5選
授業検討会を充実させるには、「教師の指導方法」ではなく「生徒の学び」に焦点を当てることが重要です。本記事では、意見が出やすい協議の進め方や授業者が萎縮しない工夫、ポジティブなフィードバックの方法など、実践的なヒントを5つ紹介します。研究授業の質を高め、建設的な議論を生み出すためのポイントも詳しく解説します。
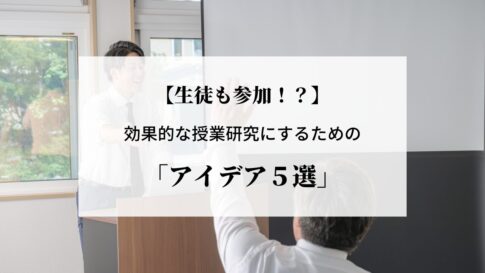 教員・教職志望の方
教員・教職志望の方授業検討会を充実させるには、「教師の指導方法」ではなく「生徒の学び」に焦点を当てることが重要です。本記事では、意見が出やすい協議の進め方や授業者が萎縮しない工夫、ポジティブなフィードバックの方法など、実践的なヒントを5つ紹介します。研究授業の質を高め、建設的な議論を生み出すためのポイントも詳しく解説します。
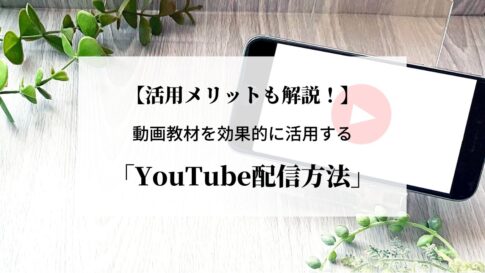 教員・教職志望の方
教員・教職志望の方自身で作成した動画を配信する際に「生徒にとって見やすいプラットフォームか」「動画管理が煩雑にならないか」など、視聴者(生徒)と配信者(教員)の手間をできるだけ取り除くことが大切です。この課題を簡単に解消してくれるのがYouTube配信です。今回は、初めてYouTube配信を行う先生に向けて、一から手順を紹介をします。
 教員・教職志望の方
教員・教職志望の方一人一台端末により動画を用いた学習は当たり前になっています。その中で自身の目的に応じた動画教材を自ら作成する必要も出てきました。しかし動画収録が一発撮りで済むことはありません。そこで今回の記事では、作成した動画を編集し、より見やすく聞き取りやすくする方法を紹介していきます。より教育効果の高い動画を目指していきましょう。
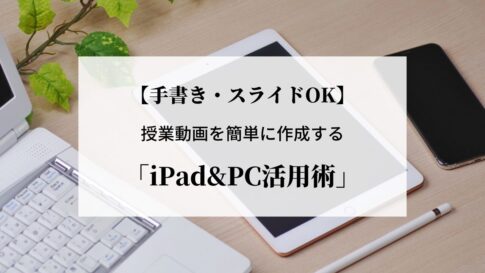 教員・教職志望の方
教員・教職志望の方一人一台端末により、動画を用いた学習や授業展開を行うことで授業の幅が大きく広がります。特に授業のねらいに応じた動画を自身で作成するメリットは大きいです。ただ、動画作成は学習や実際に作成する時間がかかります。そこで今回の記事では、普段の授業で使うのに十分なクオリティの動画を簡単につくる方法を紹介していきます。
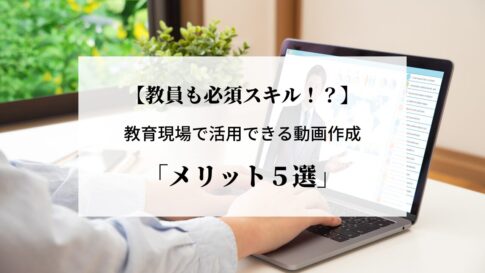 教員・教職志望の方
教員・教職志望の方これからの授業では、生徒がアウトプットをする、探究的な学びを進めていくような活動を実施していくことが必須です。そこで役立つのが独自に作成した学習動画です。実施したい教育活動にあわせた学習動画を作成することで、生徒の学びの幅は大きく広がります。そこで今回の記事では、教育活動における動画作成のメリットを紹介していきます。
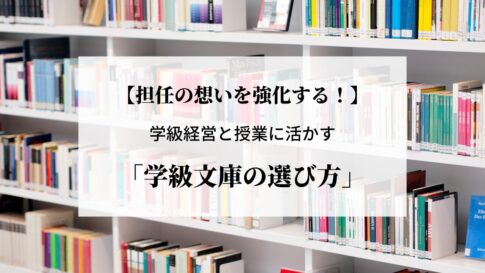 教員・教職志望の方
教員・教職志望の方学級文庫は、図書室の選書とは異なり担任が自らの想いで選書ができるスペースです。日々の教育活動の中で伝えたい想いや生徒の成長につながる考え方が得られるもの。このような担任の想いをダイレクトに反映できます。そこで今回の記事では、担任の想いを強化し生徒により伝えるために、学級文庫の役割と考え方を紹介していきます。
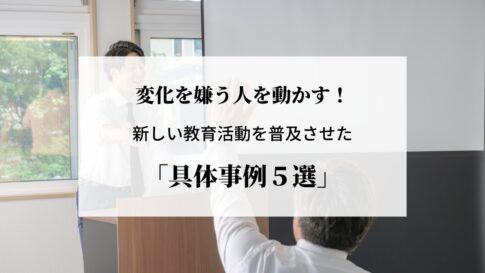 教員・教職志望の方
教員・教職志望の方変化の激しい現代、教育現場でも時代に応じた教育観が求められています。各学校には、それらの変化を敏感にキャッチして実践をしている先生方もいます。一方で、変化を受け入れられず、従来の教育から抜け出せない学校も珍しくありません。そこで今回は、変化を嫌う人の特徴を分析しながら、私自身の変化に向けた実践例を紹介していきます。
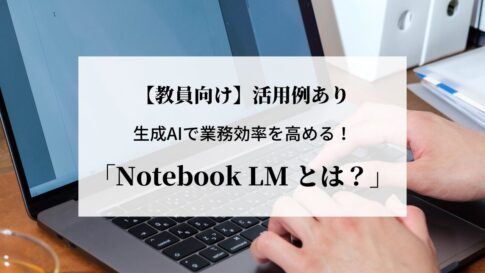 教員・教職志望の方
教員・教職志望の方よりよい教育を推進するには、ICTを使いこなしたり資料や論文などをたくさん読んだりと、学びを深めていく必要があります。しかし、多忙な教職の現場では、その時間も取ないことが多いでしょう。そこで今回は、膨大な資料から質問に答えてくれる生成AI「Notebook LM」について紹介します。
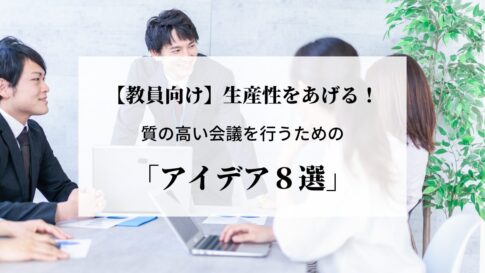 教員・教職志望の方
教員・教職志望の方学校現場は会議が多く、業務への負担が増しています。また、担当業務が個人分担されていることから、特定の議題が他人事になっている場合も見られるでしょう。「同じ行うなら生産性の高い会議にしたい。」そこで今回の記事では、よりよい教育活動が創造され、業務改善につながる会議を実施するためのヒントを紹介していきます。
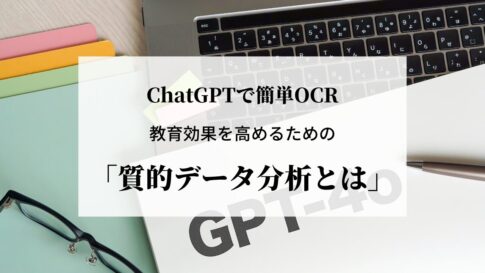 教員・教職志望の方
教員・教職志望の方教育活動を終えた際、生徒の声を拾ったり、学びの過程である成果物まで分析したりしている学校は少ないと思います。実際に行おうとすると、手書きのワークシートの分析には大変な労力がかかります。そこで今回の記事では、生徒のワークシートをChatGPTを用いて簡単にデジタル化し、分析に使えるよう整理する方法を紹介します。
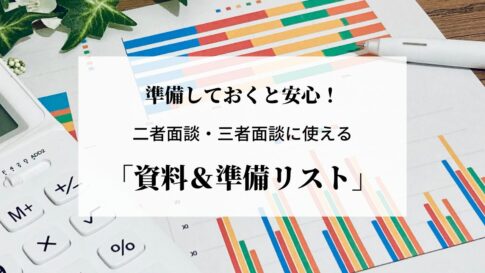 教員・教職志望の方
教員・教職志望の方高校では、二者面談や三者面談が毎年行われます。その際、どのような資料を準備しておくべきか整理しておきたい先生方も多いでしょう。今回はこれまでの実践の中で準備しておいてよかったものを22個紹介していきます。当たり前のものから、「これは!?」というものまで紹介していますので、気になるものをぜひチェックしてみてください。
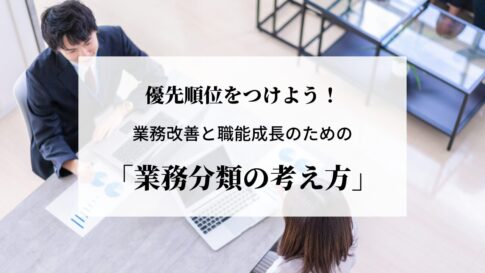 教員・教職志望の方
教員・教職志望の方教職は多忙です。一方で、これからの時代を生きる生徒のために、教育観をアップデートすることも必要です。学びの時間を生み出すために必要な視点は、業務の優先順位を決めること。そこで今回紹介をするのは「緊急でなく重要なこと」に時間をかける視点です。仕事を適切に分類することで、より質の高い業務に集中していきましょう!