アナログ課題とデジタル課題を融合する!ipad×Google Classroom仕事術
一人一台端末の推進により、教育現場でも課題提出の形が変わりつつあります。しかし、すべてをデジタル化すればよいわけではなく、学習の定着を考えればアナログの良さを活かすことも重要です。そこで本記事では、紙の課題の利点を残しつつ、デジタルを活用することで業務効率を向上させる方法を紹介します。
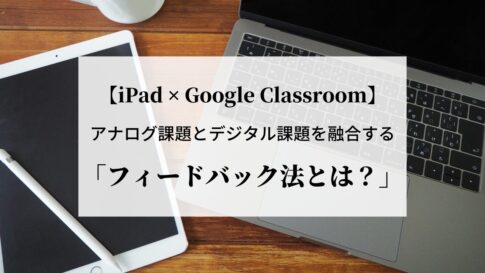 教員・教職志望の方
教員・教職志望の方一人一台端末の推進により、教育現場でも課題提出の形が変わりつつあります。しかし、すべてをデジタル化すればよいわけではなく、学習の定着を考えればアナログの良さを活かすことも重要です。そこで本記事では、紙の課題の利点を残しつつ、デジタルを活用することで業務効率を向上させる方法を紹介します。
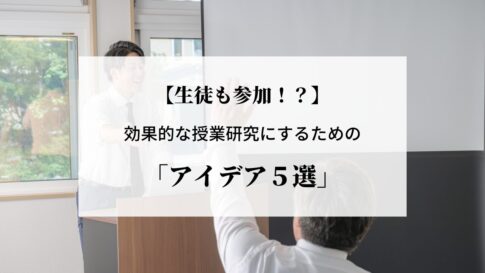 教員・教職志望の方
教員・教職志望の方授業検討会を充実させるには、「教師の指導方法」ではなく「生徒の学び」に焦点を当てることが重要です。本記事では、意見が出やすい協議の進め方や授業者が萎縮しない工夫、ポジティブなフィードバックの方法など、実践的なヒントを5つ紹介します。研究授業の質を高め、建設的な議論を生み出すためのポイントも詳しく解説します。
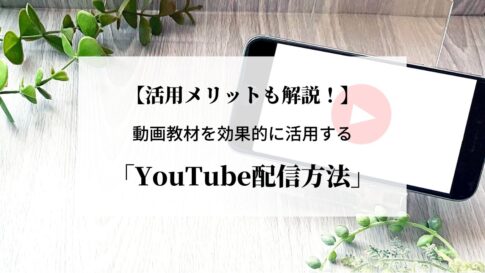 教員・教職志望の方
教員・教職志望の方自身で作成した動画を配信する際に「生徒にとって見やすいプラットフォームか」「動画管理が煩雑にならないか」など、視聴者(生徒)と配信者(教員)の手間をできるだけ取り除くことが大切です。この課題を簡単に解消してくれるのがYouTube配信です。今回は、初めてYouTube配信を行う先生に向けて、一から手順を紹介をします。
 教員・教職志望の方
教員・教職志望の方一人一台端末により動画を用いた学習は当たり前になっています。その中で自身の目的に応じた動画教材を自ら作成する必要も出てきました。しかし動画収録が一発撮りで済むことはありません。そこで今回の記事では、作成した動画を編集し、より見やすく聞き取りやすくする方法を紹介していきます。より教育効果の高い動画を目指していきましょう。
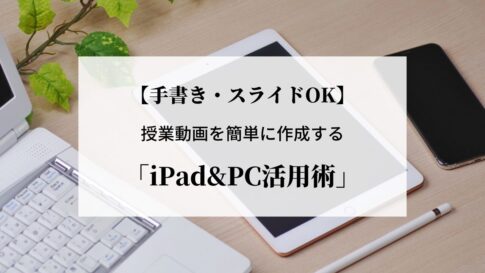 教員・教職志望の方
教員・教職志望の方一人一台端末により、動画を用いた学習や授業展開を行うことで授業の幅が大きく広がります。特に授業のねらいに応じた動画を自身で作成するメリットは大きいです。ただ、動画作成は学習や実際に作成する時間がかかります。そこで今回の記事では、普段の授業で使うのに十分なクオリティの動画を簡単につくる方法を紹介していきます。
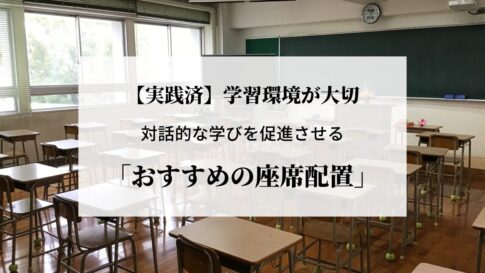 教員・教職志望の方
教員・教職志望の方近年は、主体的・対話的で深い学びを目指した授業展開が求められます。しかし、多くの学校で、一斉授業に適した全員が黒板の方向を見ている座席になっています。この座席を少し工夫することで、生徒同士の対話と学びが一気に深まります。今回の記事では、効果的に学習を進めるための座席配置について紹介します。
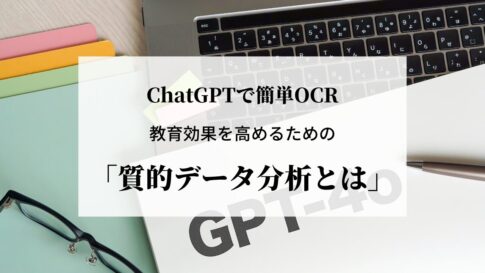 教員・教職志望の方
教員・教職志望の方教育活動を終えた際、生徒の声を拾ったり、学びの過程である成果物まで分析したりしている学校は少ないと思います。実際に行おうとすると、手書きのワークシートの分析には大変な労力がかかります。そこで今回の記事では、生徒のワークシートをChatGPTを用いて簡単にデジタル化し、分析に使えるよう整理する方法を紹介します。
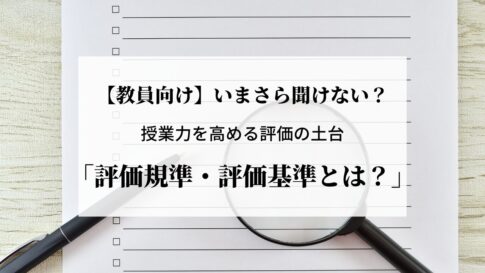 教員・教職志望の方
教員・教職志望の方「評価規準」と「評価基準」。指導案などで指摘されたことがある先生も多いと思います。教員として大切な仕事の一つである評価。適切な評価は生徒の成長を促します。また評価をしっかり考えることは、授業をよりよくすることにもつながります。今回は、評価の土台である2つの「きじゅん」について、分かりやすく解説していきます。
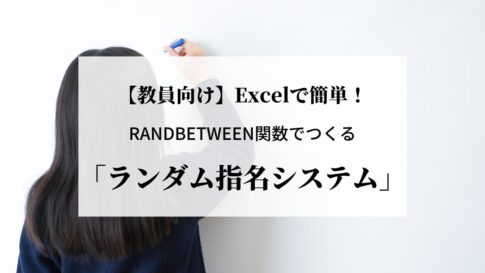 教員・教職志望の方
教員・教職志望の方授業で指名するとき、意図的に指名するのが一般的です。一方で、中には席順など機械的に指名をする方もいます。しかし、これではあまり教育効果が期待できません。今回はExcelを使ってランダム指名をするためのシステムを紹介し、「主体的・対話的で深い学び」との関連性についても紹介をしていきます。
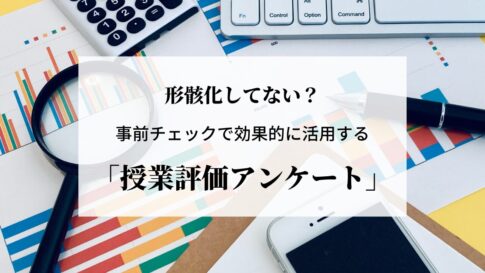 教員・教職志望の方
教員・教職志望の方毎年行われる授業評価アンケート。実際のところ形骸化してしまっていませんか?今回は、業務負担にも感じられる「授業評価アンケート」を効果的に活用するヒントを紹介します。意味のあるものにすれば、自身の授業力向上に役立つ授業評価。事前(項目確認)→実践(授業)→事後(振り返り)のサイクルで授業改善を進めていきましょう。
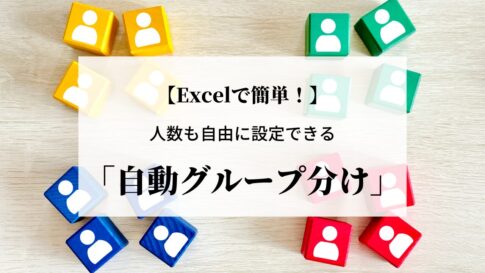 教員・教職志望の方
教員・教職志望の方授業でグループ学習を行っている先生は多いですよね。ただ、番号順や教室の座席配置だと、いつも同じメンバーで学習をすることに。すると、人間関係が固定化される、多様な意見を聞く環境ができない、仲良しグループで活動がマンネリ化するなどのデメリットもあります。今回は、Excelで簡単にグループ分けが作成できる方法を紹介します。
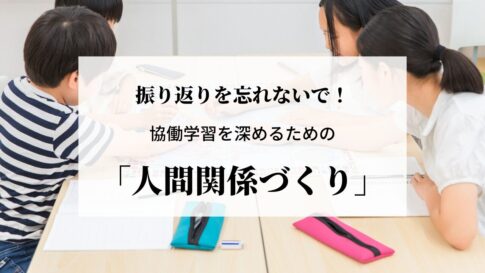 教員・教職志望の方
教員・教職志望の方協働学習のために取り入れるグループ活動。でも実際に行うと、おしゃべりで終わったり対話が深まらなかったりすることも。これは、グループ学習の取り組み方が分からない、そもそも人間関係ができていない場合があるのです。今回の記事では、協働学習を効果的に進めるための人間関係づくりワークと教科学習に活かす振り返りについて紹介します。