
効果的なインプットのためには、アウトプットの場を用意してあげることが大切です。
教員はアウトプットの場がたくさんありますよ!
「教員としてスキルアップするために学びたい。」
「でも日々の業務が忙しくて、効率よく学ぶことができていない。」
そのような悩みを抱えている先生方は多いのではないでしょうか?
スキルアップのためのインプットには読書が最適です。
しかし、ただ読書をしただけでは自身の力を高めることは難しいでしょう。
そこで大切な要素がアウトプットの場面を積極的に用意することです。
今回は、アウトプットを前提とした読書術と日々忙しい教員のための時間捻出法について紹介します。
効率よく学びを続け、目の前の生徒にとって「学びのロールモデル」となれる教員を目指していきましょう。
高校の数学教員として10年以上教職に携わる。
内容を教えるのではなく、学び方を教えるをモットーに授業を展開。
様々な実践を掛け合わせることで、目の前の生徒に応じた教育活動を実現。
また、教育分野以外からの学びを学校教育に活かすことを意識している。
目次
教員にとって読書は必須

教員としての資質・能力を高めるためにはどうしたらよいでしょうか…。

日々学び続ける姿勢を持つことが大切ですね。
教員は学習内容を教えるだけでなく、日々変化する生徒や教育情勢に応じて自分自身も成長していく必要があります。
そのためには、
- 自身の専門性を高めること
- 人間性を向上させること
- 学び続ける姿勢を見せること
が大切です。
専門性を向上させることは、より深い学びを生徒に提供することにつながります。
また、教科の専門性だけでなく、学級経営や進路指導、生徒指導など多岐にわたる業務を行うためには、社会情勢を把握したり豊かな人間性を創り上げたりしていくことも大切です。
そのためにも、教育分野に限らない幅広いジャンルについて教養を深めていかなければなりません。
そして何より「学ぶ」ことを教える教員自身が、誰よりも学ぶ姿を見せることが大切なのです。

確かに学ぶことって大切ですね。

学び方にはいろいろな種類がありますが、読書は特にオススメです!
学びの形態はたくさんあります。
- 研修に参加する
- セミナーを受講する
- 人と会って情報交換をする
どれも意義のある学びの機会です。
しかし、最も基本的な学びは読書でしょう。

読書の時間が教師としての資質・能力を高めてくれるのです。
一方で、教員は多忙な日々を送っており、なかなか読書の時間を取ることができません。
読書の時間を設けたとしても、「何となく読んで終わり」となってしまい、教職に活かせていないことも多いのです。
せっかく時間をかけて学ぶのですから、それらが教師としての成長につながるようにしていきたいですね。
教師のための読書術

読書をより効果的にするための方法を教えてください!

それはアウトプットを前提に読書を行うことです!
多くの人は、1冊の本を通して新しい気づきを得た段階で学びを終わりにしてしまいます。
しかし、アウトプットを前提にすることで読書の効果は大きく変わります。
以下、詳しく紹介していきます。
アウトプットの重要性と種類

まずは、改めてアウトプットの重要性について話しをしておきます。
先ほども述べたように、アウトプットの場面を設けることで、インプットが深まります。
これは毎日の授業で生徒にも伝えていますよね。
一方向に教員の話を聞くだけだったり、ただ教科書を読んだりしているだけでは、学習内容は身につきません。
問題を改めて解いたり、自分でテストを作ったりする。
また、他者に説明したり表現したりすることで、学びはより深まります。

適切な学習方略を立てたり、協働学習をしたりってことですね。
そしてもっと言えば、授業でアウトプットの場面を設定することを事前に生徒に伝えておくことが大切です。
初めからアウトプット前提にインプットを行うことで、より学習の質が高まり学びが深まるのです。
私の授業では、初めから生徒が問題の解説をすることを前提としています。
すると生徒たちは自分たちで問題を進め、必要に応じて解決方法を調べたり友達と協働したりしています。
このようにアウトプットの場面を準備することは効果的な学びにつながるのです。

では、教員に当てはめてみましょう!
私自身は以下のようなアウトプットを前提に取り組んでいます。
これらは全てアウトプットです。
このようなアウトプットを行うことで、多くのメリットを得られます。

このようなメリットもあり、アウトプットを始めてから、読書の量や効率がぐっと上がりました。
アウトプットのためのインプット〜3色ボールペンと4色の付箋を活用しよう
上記のようなアウトプットを行うためには、インプットも合わせて工夫していく必要があります。
そこで私が実践しているのが、3色ボールペンと4色の付箋の活用です。
この手法は目新しいものではないのですが、アウトプットに役立つ方法ですので参考にしてみてください。

本に書き込みをしながら読んでいくのですね!

自分なりにルールを決めてチェックを入れていきましょう!
私は以下のようにルールを決めています。
赤:重要なこと、新しい発見
青:引用できそうな内容
緑:関心が広がった、面白いと思ったアイディア
まず本を読みながら、上記の基準に沿ってチェックまたはラインを引いていきます。
そして同時に同じ色の小さい付箋をそのページに貼っておきます。
これは、線を引いただけでは本を閉じた後、どこに線を引いたかを一枚一枚探さなくてはならない手間を省くためです。
図のような小さい付箋を貼っておけば、どのページにどの色のラインをつけたががすぐにわかるのです。

ポストイットはちょうど赤・青・緑が揃っています。
そして残りの黄色の付箋は、図や表で気になったページに貼っておきます。
文章はもちろんのこと、図や表は引用にも活用できますし、先生方への情報提供にも最適です。

ちょっと大変そうに思われるかもしれませんが、改めて情報を探すときに検索しやすいのです。
3色のラインと4色の付箋を活用することで、気になったときにすぐ情報を引っ張ることができます。
仕事をしている際に
「昔読んだなぁ」
「あのデータを生徒・先生方に示そう」
と思うことはありませんか?
そのようなときに、簡単に見つけ出しアウトプットに活用しやすくなるのです。

これなら頭の片隅に残っている知識でも、必要なときに引き出せそうですね。

「せっかく読んだのに、活用する場面が訪れない」というのは、もったいないですからね!
読書の記録をつける

さらに読書をしながら、アウトプットに活かせそうなものはその場で記録します!
「ボールペン&付箋」読みは、気になった部分にどんどんチェックを入れていくものです。
したがって、情報量がとても多くなります。
これは知識がどこで結びつくかわからないので、「学びになった」「面白い」と思ったものに、次々チェックを入れていくのです。
一方で、すべてのチェックがすぐに活用されるとは限りません。
ですから学級通信・ブログ・Twitterなど、すぐに活かせそうなものはその場で記録をつけておきます。
私自身は読書記録に、以下のアプリを長年利用しています。

上記のアプリは「アイデアの記録」と「書籍全体の記録」で使い分けています。
Evernote&FastEver
「Evernote」 は、多くの方が利用している有名アプリです。
テキスト以外にも、画像・動画・音声ファイルなど多種多様なデータを保存できるのが魅力的です。
ノートをブックごとに分けることができるため、「読書ブック」を作成し、そこに次々とアイデアを書き込んだノートをブックとして溜めていきます。
そうすることで、他の仕事のメモと区別しながら整理ができます。
また「学級通信」「分掌会議提案」「ブログ」「Twitter」など、タグを利用することもできるので、検索性にも優れています。

ただボールペンで線を引くだけより、よりアウトプットに使える形になりますね!

すぐには活用しなくても、後でアウトプットに使いそうな内容は、メモをして整理をしておくとよいでしょう。
大変便利なEvernoteですが、無料アカウントでは「同期端末が2台まで」という制限があります。(2023年5月現在)
そこで利用しているのが 「FastEver」 です。
FastEverを使えば、スマートフォンからも気軽にメモを取ることができます。
Evernoteの同期端末は、Mac BookとiPadで使用し、iPhoneからはFastEverを利用してメモをとります。
メモしたいときに、すぐに取り出せる点で iPhone は便利です。
FastEverからもノートやタグを選択できますので使い勝手がとてもよいのです。
また画像や写真を貼り付けることができるので、メモと同時に本を写真で撮っておくのもオススメです。

読書メモを活用し、アウトプットのネタを溜めようとすることで、インプットの質も高まります。

デジタルで管理すれば、検索も簡単で必要なときに情報を引き出せますね。
ビブリア
もう一つ読書記録としてオススメするアプリは「ビブリア」です。
こちらは読書管理アプリで、これまでに読んだ本をデータベースとして蓄積することができます。
書籍全体の記録をしておけば、改めて情報を引き出したいと思ったとき、関連する書籍をすぐに見つけることができます。
また学びが大きかったものに「☆5」をつけておけば、読み直しのときの優先順位にもなります。
このように、ざっくりとした読書記録をつけておくことで、将来的なアプトプットに活かすことができるのです。

「気になる情報」と「書籍全体」でメモしておくのですね。

アウトプットを短期と長期の時間軸に分けて、読書の記録を取るとよいですね!
- 今すぐアウトプットできそうな内容は、Evernoteを用いてアウトプットに近い形でメモする。
- 将来、立場や担当する仕事が変わったときに必要になるかもしれない内容は、いつでも読み返しができるようにビブリオでざっくりとしたメモを残しておく。
このように「ボールペン&付箋」というアナログのインプットを、時間軸で分けてデジタル管理するようにしています。
読書をするための時間が捻出できない方へ

確かにアウトプットを意識してメモを取ると、インプットが深まりそうです。でもなかなか時間が取れないですよね。
ここまで、アウトプットを前提とした教師のための読書術について説明をしてきました。
しかし多忙な教職において、なかなか読書の時間を確保できない方もいると思います。
そのような方のために、読書や学びのための時間づくりについて紹介します。
朝の時間を有効に使う

一番のオススメはやはり朝の時間を有効に利用することです。

朝活ですね。朝はちょっと苦手ですが頑張ろう…。
朝の時間を学びに充てることはとても有効な時間の使い方です。
これは教員である我々が一番よく知っていることですよね。
日ごろから、生徒にも朝の学習を推奨しています。
これらは、私が生徒にいつも言っていることです。
「人に言うなら、まずは自分から」ということで実践をしています。
朝型・夜型という言葉がありますが、やはり朝型のメリットは大きいです。
朝活を実践していくためにも、やりたいことの優先順位をしっかり決めて、夜は早く寝てしまうのがよいでしょう。
そして朝に効果的な読書を行うことで、インプットもアウトプットの質も高まって行きます。
拘束時間を利用する

拘束時間ってどのような場面でしょう?

待ち時間など、他のことができないときが読書のチャンスです!
まとまった時間をつくることができなくても、スキマ時間を活用して読書を進めることはできます。
これも、日ごろから生徒に伝えていることですね。
体が拘束されているだけで、時間を持て余しているときは読書のチャンスです。
学校でのスキマ時間
例えば、学校現場で見てみましょう。
部活動が終わってから生徒が帰宅するまでの時間は、割と時間がとれます。
片付けや戸締り、鍵の返却などを待っているときは、まさに「帰れない、でもやることはない。」状態です。
放課後から職員会議までの時間は、まとまった時間がとれません。
ですから、仕事を始めても中途半端に終わってしまうでしょう。
そこで割り切って早めに会議室にいき、読書をしてしまうのもあり。
この時間にちょっとでも仕事をしようとする先生も多いので、大抵は時間通り会議は始まりません…。

意外とスキマ時間ってありますね。

勤務時間内であれば、教育資料などを読む。
部活終わりは勤務時間でないので、何でもOKです!
プライベートでも本を持ち歩く
一方でプライベートな時間もスキマ時間はたくさんあります。
新書や電子書籍などであれば、気軽に持ち歩くことができます。
例えば、病院の待ち時間などがよい例です。
教員は毎年人間ドックを受ける方も多いでしょう。
このようなスキマ時間にスマートフォンで暇を潰すか、読書をするかで大きな差が出てくるのです。
通勤時間を活用する
通勤時間も立派な読書のチャンスです。
電車であれば、少しでも混雑を避けれるよう少し早めに出勤すれば落ち着いて読書ができます。
自家用車で通勤されている方は、オーディオブックなどで読書の代わりにすることもできます。
運転中は3色ペンや付箋は使えませんから、運転終了後に先ほど紹介した読書アプリにさっと音声入力などでメモしておくとよいでしょう。

生徒に「スキマ時間に学習を」とよく言っていましたが、自分ができていなかったですね。

それぞれの生活スタイルに合わせて、時間を見つけてみましょう!
職務に関係するものは勤務時間でも

先ほど、勤務時間中のスキマ時間の話が出てきましたが、勤務中に読書ってありなのでしょうか?

職務に関係するものであれば、大丈夫でしょう。
公務員には職務専念義務があります。
ですから、職務に関係ない読書は許されません。
たまに、空き時間に小説を呼んでいる人を見かけますが、それはNGです。
教員には、幅広い教養を身につけることが求められています。
その点で、多くのジャンルの書籍が職務に関係しそうです。
ですから、他の公務員よりも勤務時間中の読書への制限は緩いでしょう。
しかし、職場での信用を失わないためにも、空き時間は職務に直接関係するものに限定しておきましょう。
表紙が明らかに教育に関係するものであれば、特に注意されることもありません。
また、行政関係が発行している資料も学びのための立派な読書です。
これらに目を通していれば、注意されるどころか逆に勉強熱心であるとして評価されるものです。
一方で、仕事を効率よくこなすことで教育書を読む時間をつくっていたとしても、同僚の目には時間を持て余しているように見えることもあります。
それが原因でトラブルを起こした例もたまに耳にします。
ですから、日ごろからの同僚との関係性と何を読むかには気をつけておきましょう。
すべてを読もうとしない

最後の時間捻出のためのポイントは「すべてを読もうとしない」ことです。
本を一冊読むためには、それなりに時間がかかります。
全章・全項目を一字一句じっくり読もうとすると、1冊だけで1ヶ月が終わってしまうこともあるでしょう。
ですから、すべてを読もうとしないことがポイントです。
初めは流し読み、雑誌の場合は気になった記事だけを読むなど工夫をして読むのです。

ここで活躍するのが、3色ペン&付箋の力です!
流し読みをしたとしても、いま自分が求めている情報が出てきたときには、多くの場合が目に留まります。
逆にすぐに必要でない情報は、読み飛ばしても構わないのです。
そして目に止まったその内容が
このような視点でラインを引いて、付箋の目印をつけておくのです。
そうすることで重要な部分はメモに残せますし、仮に内容が頭から抜けてしまっていても、今後に活用できる知識として保存しておくことができるのです。

ただの流し読みだと学びに結びつかない気がしてましたが、アウトプットとセットなら自分の力につながりそうです。

「○○なときに使える本」などのメモをしておけば、読み直しもしやすいですね。
まとめ:アウトプットを意識した読書習慣を身につけ、学び続ける教師を目指そう
今回の記事では「アウトプットで高める教師の読書術&時間捻出法」について紹介してきました。
教師にとって大切な要素は、
- 自身の専門性を高めること
- 人間性を向上させること
- 学び続ける姿勢を見せること
などが挙げられます。
これらを実現させるために、教師は学び続けることが必須であり、中でも基本的な学びの形が「読書」です。
しかし、学びのための読書は、ただ読んで終わりとなってしまいがち。
そうならないためにも、アウトプットを前提としたインプットとしての読書を心がけましょう。
このようなアウトプットを意識することで、読書の質を高めることができます。

アウトプットを意識した読書では、「書籍への書き込み」と「メモ」が大切でしたね。
3色ボールペンと付箋を活用し、いつでも書籍から情報を引っ張ってこれるようにすることで、知識を体系化していきます。
また、アプリを活用することで、デジタルでのメモをとり、検索性の向上も図るとよいでしょう。
赤:重要なこと、新しい発見
青:引用できそうな内容
緑:関心が広がった、面白いと思ったアイディア

アウトプット前提するとインプットが楽しくなりそうです!

ボールペンのルール作りや使用するアプリは、人それぞれ。
自分好みにやってみましょう!

効果的なインプットのためには、あとは時間の捻出でしたね。
アウトプット前提の読書には、時間がかかります。
多忙な教員ですから、読書時間の捻出にも工夫することが大切です。

優先順位を決めること、スキマ時間の活用でインプットの時間を確保していきます!
社会の変化が激しい近年、教師の学びの質と早さが求められています。
以前からの「学び続ける教師像」は、ますます重要性が高まってきています。
これからは、学ぶだけでなく、その学びを実践し、自ら発信をしていく。
そのような教師像が求められるでしょう。
そのための一つの形として、アウトプットを前提とした読書をぜひ行ってみてください。

今回の記事が、学びに向かう先生方のヒントになれば嬉しいです。
▼今回の記事に興味を持ってくださった方は、こちらの記事もどうぞ!
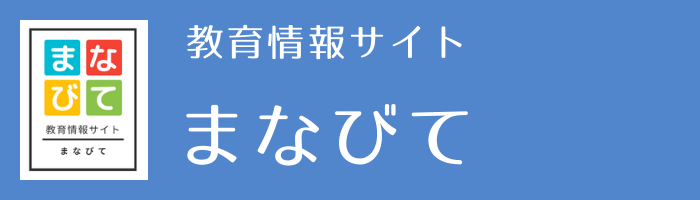
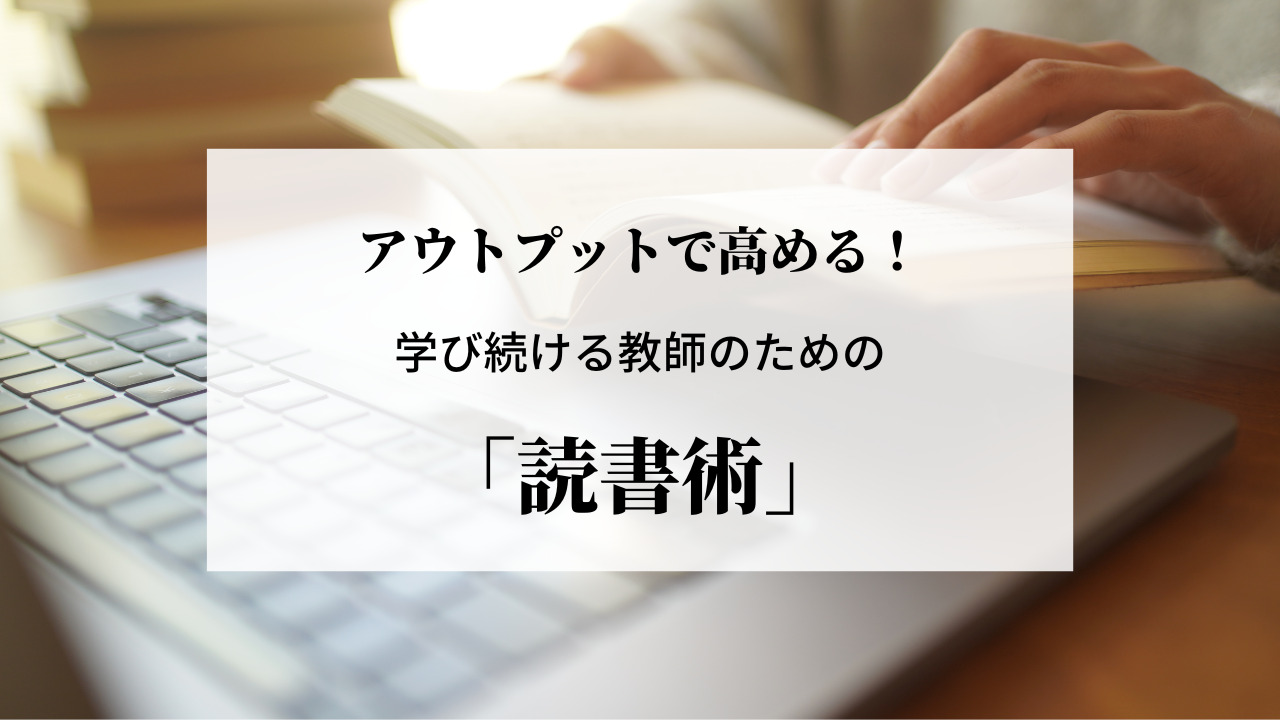


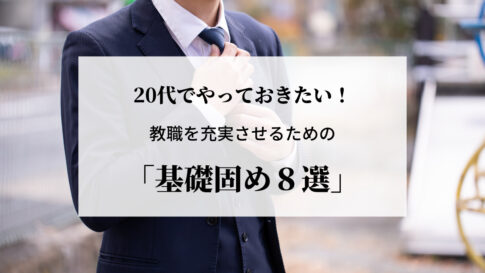
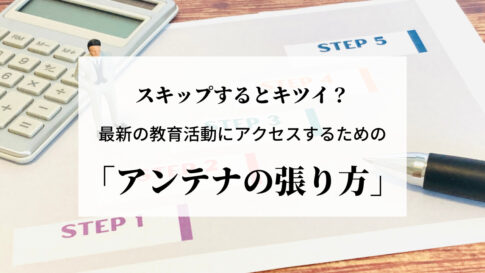
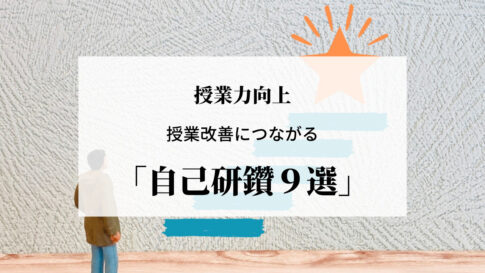
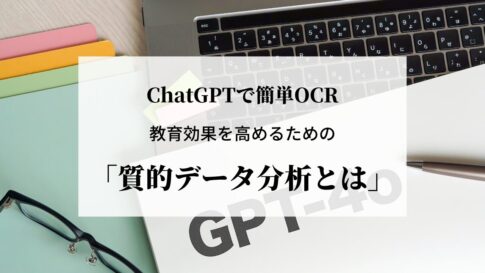
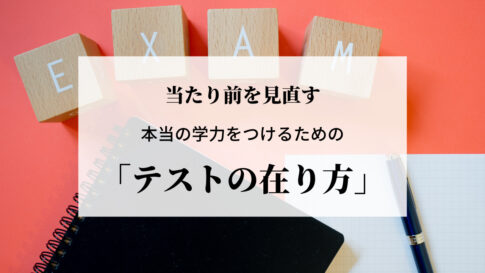
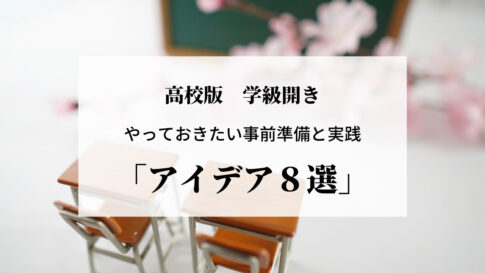
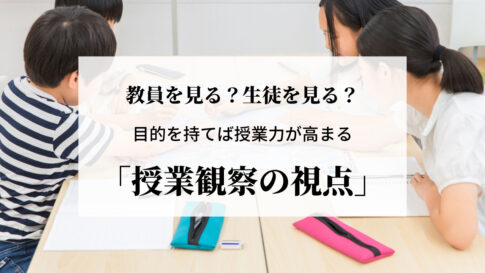
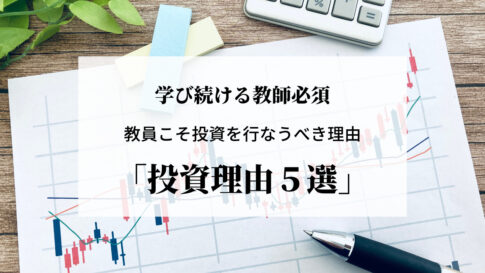
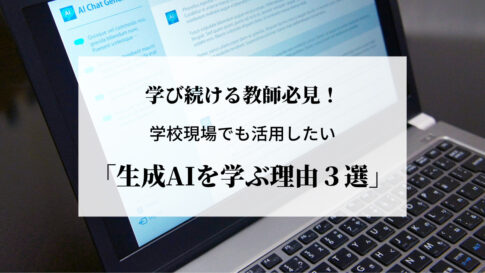
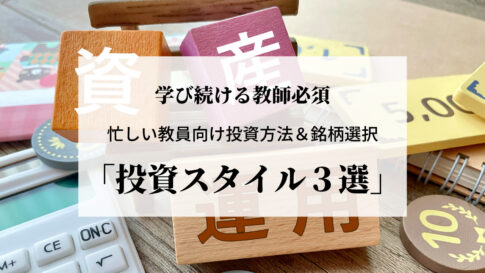
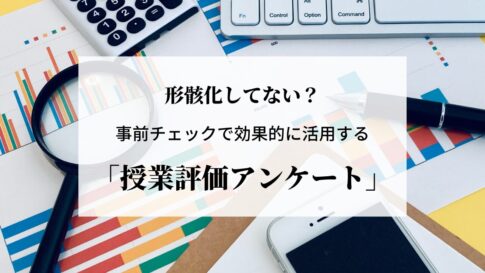










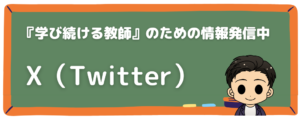
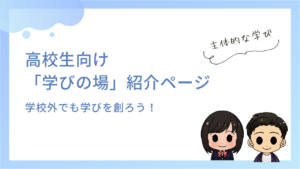
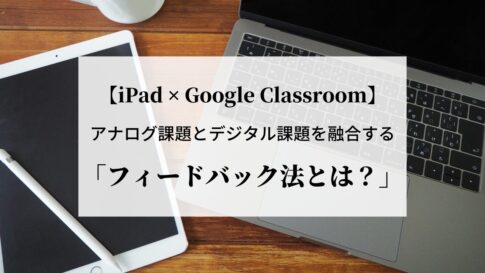
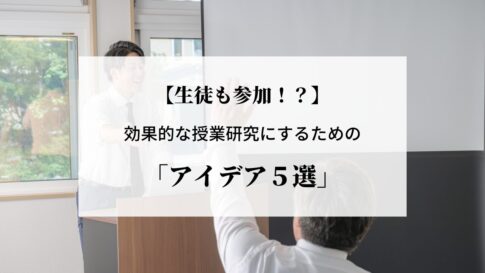
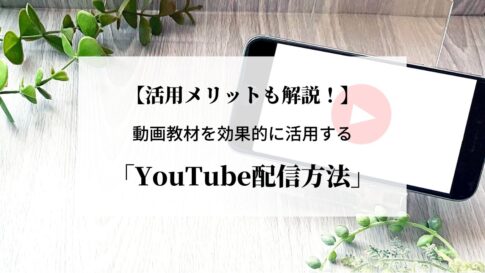

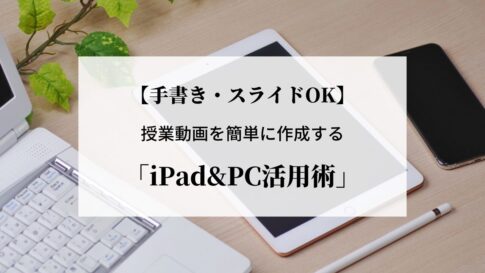
教員としてのスキルアップのために読書をしたいのですが、時間も取れないし実践にもつながっていない気がしています…。